UXデザインと心理学をWebアプリ/スマホアプリでの活かすには
デザイン 🕒 2025年4月11日
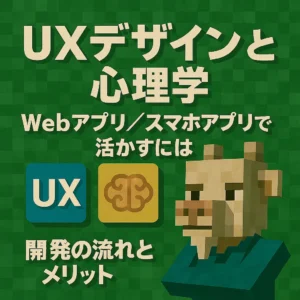
――10の“人間らしさ”を味方にする設計原則――
目次
はじめに
ユーザーインターフェース(UI)を磨くだけでは、心地よいユーザー体験(UX)は生まれません。鍵になるのは 「人間の認知特性」 を理解し、デザインに落とし込むこと。本記事では、プロダクトづくりに欠かせない 10 の心理学的法則を取り上げ、意味・理由・実践ポイント・Webアプリ/スマホアプリでの生かし方 をセットで解説します。
1. ヤコブの法則(Jakob’s Law)
人は“慣れた操作感”を好む
- 要点:ユーザーは他サイトで得た経験を基準に新しいサイトを評価する。
- UX実践
- 業界で定番のナビゲーション配置や用語を尊重する。
- “革新”より“既視感”を優先し、学習コストをゼロに近づける。
- Webアプリ/スマホアプリでの例:新規 SNS を作るなら、プロフィール編集や「いいね」ボタンの位置・アイコンを Instagram/X とほぼ同じにすることで、チュートリアル無しでも操作できる
2. フィッツの法則(Fitts’s Law)
クリックしやすさ = 距離 ÷ 大きさ
- 要点:ターゲットが大きく近いほど操作は速く正確になる。
- UX実践
- 主要ボタンを十分なサイズで配置。
- 右利きユーザー向けにスマホ親指ゾーンへ CTA を置く。
- Webアプリ/スマホアプリでの例:スマホ決済アプリの「支払う」ボタンを画面下部いっぱい(親指ゾーン)に配置し、角を丸めてタップ領域を実サイズより広く取る。
3. ヒックの法則(Hick’s Law)
選択肢が増えるほど意思決定は遅くなる
- 要点:選択肢 n 個 → 認知負荷は log₂ n に比例。
- UX実践
- メニューを 5〜7 項目に絞り、残りは“その他”へ。
- ステップ分割(例:1/3、2/3、3/3 ウィザード形式)で迷いを減らす。
- Webアプリ/スマホアプリでの例:旅行予約アプリの検索画面で、日付・人数・部屋タイプなどはステップ式ウィザードに分割し、一度に表示する選択肢を 5 項目以下に抑える。
4. ミラーの法則(Miller’s Law)
短期記憶の魔法数は 7±2
- 要点:人が一度に保持できる情報は 5〜9 チャンク。
- UX実践
- 電話番号を 3‑4‑4 桁で区切る。
- 表やカードを 3×3 グリッドで整理し、視覚的チャンク化を促す。
- Webアプリ/スマホアプリでの例:タスク管理アプリの「今日やること」リストを最大 7 件だけ表示し、残りは「もっと見る」で折りたたむ。
5. ポステルの法則(Postel’s Law / Robustness Principle)
入力に寛容、出力は厳密に
- 要点:受け取るデータ形式には柔軟に、返す形式は一貫性を保つ。
- UX実践
- フォームで「09012345678」「090-1234-5678」どちらも許可。
- エラーメッセージは具体的に「半角 10〜11 桁で入力してください」。
- Webアプリ/スマホアプリでの例:住所入力フォームで「1‑2‑3」や「1丁目2番3号」など複数フォーマットを自動変換し、保存時は「東京都千代田区1‑2‑3」に統一。
6. ピークエンドの法則(Peak‑End Rule)
体験は“最高潮”と“終わり”で評価される
- 要点:平均よりもピークとエンドの感情が記憶に残る。
- UX実践
- サービス登録完了時に達成感のあるアニメーションを表示。
- サポートチャットの最後に感謝と次のステップを提示。
- Webアプリ/スマホアプリでの例:食事記録アプリで、目標カロリーを達成した日は花火アニメ+称賛メッセージを表示し、1日の締めくくりに「今日の成果」をカードで見せる。
7. 美的ユーザビリティ効果(Aesthetic‑Usability Effect)
美しいものは“使いやすい”と感じやすい
- 要点:第一印象の良さが小さな欠点を許容させる。
- UX実践
- 余白・タイポグラフィ・配色を整え、瞬時に“洗練”を伝える。
- ただし装飾過多でパフォーマンスを損なわないよう注意。
- Webアプリ/スマホアプリでの例:フィンテックアプリの残高画面を、余白とモーションを生かしたカードUIで美しく見せることで、残高更新の待ち時間(1 秒程度)への不満を軽減。
8. フォン・レストルフ効果(Von Restorff / Isolation Effect)
周囲と異なる要素は記憶に残る
- 要点:コントラストが高い項目ほど注目度が上がる。
- UX実践
- 価格表でおすすめプランだけカードを拡大・色変更。
- エラー入力欄を赤枠+アイコンで際立たせる。
- Webアプリ/スマホアプリでの例:サブスクプラン比較ページで、推奨プランのカードだけ背景をグラデーション+リボン付きアイコンにし、視線を集中させる。
9. テスラーの法則(Tesler’s Law / Law of Conservation of Complexity)
複雑さは“総量保存”される
- 要点:プロダクトに必要な複雑さをゼロにはできない。
- UX実践
- ユーザーの負荷を減らすために、裏側で自動化やデフォルト値を設定。
- どうしても難しい操作はガイドツアーで“学習コスト”を前払い。
- Webアプリ/スマホアプリでの例:写真共有アプリで、AI が自動タグ付け・圧縮を行い、ユーザーは「アップロード」ボタンを押すだけにして複雑さをバックエンド側に吸収。
10. ドハティのしきい値(Doherty Threshold)
応答が 400 ms 未満ならユーザーは“待ち”を感じない
- 要点:インタラクションのフィードバックは 0.4 秒以内が理想。
- UX実践
- API 呼び出しにスケルトンスクリーンやローディングバーを即時表示。
- 重い処理はバックグラウンド実行+完了通知。
- Webアプリ/スマホアプリでの例:チャットアプリのメッセージ送信時、0.3 秒以内に「送信中…」のステータスを即表示し、バックエンド処理が完了したら既読チェックマークに切り替える。
おわりに
心理学のエッセンスを知れば、「なんとなく使いやすい」を再現性のある設計指針へ昇華できます。
次にデザインをレビューするときは、上記 10 項目のチェックリストを横に置き、「どの法則を活かせるか?」と問いかけてみましょう。それだけでユーザーの心に寄り添った UX が一歩近づきます。

プログラミング好き神戸在住でADHD 【 経歴 】ニート→職業訓練→独学→正社員→フリーランス→起業
現在はリモート案件 など フリーランスエンジニア 兼 株式会社ヲタクリエイト 代表
得意言語 PHP Javascript Python Dart
フレームワーク Laravel Vue.js Flutter
取得資格:基本情報技術者、情報セキュリティマネジメント